
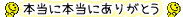
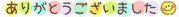


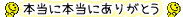
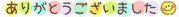




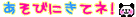
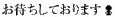

お待ちしております♪

出勤しました









年越し蕎麦は英語で「buckwheat new years eve」と言うそうです🧐
その歴史は、鎌倉時代からはじまります。
当時、博多のお寺で年を越せない程貧しい人々に、「蕎麦餅」と呼ばれる蕎麦粉で作った餅をふるまいました。
すると翌年から、蕎麦餅を食べた人々の運気が上がり、蕎麦餅を食べればいいことがあるという噂が広がりました。
それから毎年食べられるようになり、それが現在でいう年越し蕎麦となったそうです。
もともと蕎麦は、お寺で精進料理として食べられていました。
しかし次第に、貴族や武士、庶民へと広まり、日本全国で食べられるようになったとされています。
<img alt="年越し蕎麦に込められた意味" id="01082_2" src="https://cdn-img.ielove.co.jp/ie_column/01082_2_640_640_3.jpg?t=1672455740” style=”background-image: none; background-attachment: scroll; border: 0px none; box-sizing: border-box; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 1.2rem; max-width: calc(-30px + 100vw); width: 360px; border-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;” />
そもそも、簡単に作れる料理である「蕎麦」を何故大晦日に食べるのでしょうか?
それは、年越し蕎麦には込められた意味があるからなのだそうです。
1・長生きできるように
蕎麦のように、細く長く過ごせることを願って食べられます。
2・今年の不運を切り捨て、来年を幸運で迎えられるように
蕎麦は切れやすいため、今年の苦労や不運を綺麗に切り捨てて、新しい年を迎えるためと言われています。
3・金運が上がりますように
昔の金銀細工師は、細工で散らかった金や銀を集めるために、蕎麦粉を使っていたと言われています。
そのため、蕎麦で金を集めることから、金運が上がるとされました。
4・来年も無病息災でありますように
蕎麦は風雨にさらされても、日光を浴びると再び元気になります。
そのため蕎麦のように、何度も元気に蘇るようにという願いが込められています。
なるほど❣️納得🧐🧐🧐






昔から、毎年お正月には「年神様」と呼ばれる神様が各家庭へ訪れると言われています。
年神様は特定の宗教による神様ではなく、その年の福や徳を司る「歳徳神」や祖先の霊、穀物の神といったいくつもの神様がひとつにまとめられ、民間信仰と
して伝わってきたものだとされています。
正月飾りの中でも、門や玄関前に飾る門松は、年神様が家へ尋ね入るにあたっての目印だとされています。
一年中落葉しない松、成長が早く生命力の強い竹、新春に開花し、年始にふさわしい梅と3つの縁起物が用いられます。
門松といえば竹を立てたものがよく知られていますが、地域によって、松の枝に水引をかけて飾る門松や、紙に門松の絵を印刷したものを貼るといった飾り方も見られるそうです。
家の門や玄関につけられるしめ飾りは、神社で見られるしめ縄と同じように、神様が宿る場所の印です。
災厄を払うものだとも言われ、伊勢地方などでは素戔嗚尊が当地を訪れた際の民話とともに、一年中しめ飾りをつける慣習が残っています。
ひと昔前は車の正面などにもしめ飾りをつけたものですが、最近はほとんど見かけなくなりました。
年神様にまとめられたとされる神様には歳徳神に祖先の霊、それから穀物の神様もいます。
鏡餅は年神様へのお供え物です。
餅は青銅鏡、橙は玉、串に刺された干し柿は剣と、それぞれ三種の神器に見立てた飾り方が昔ながらの鏡餅ですが、最近は串柿が省かれたり、扇や伊勢海老に見立てた飾りを加えたりと、飾り方も多様化しているようです。
クリスマスリース⏩⏩⏩しめ縄リース
アレンジして玄関飾りにするのが今風かもしれませんね😅😅😅
そんなこんなの🎍門松&お正月飾りのお話でした。
年末年始を満喫しましょ😊😊😊

蕎麦・・・順番間も無く❣️

✨💖✨by satonaga jun✨💖✨



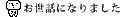




現在では年籠り本来の意味は薄れたものの、「日付が変わるまで起きておく」「夜中に初詣に行く」などが習わしとして残っています。
「晦日」とは、各月の最終日のことです。
「つごもり」は月が隠れるさまを表した「月籠り」が転じた呼び名、「かいじつ」は「晦日」の音読みなんだそうです。
小晦日は「晦日」のように複数の呼び方は無く「こつごもり」以外の読み方はないそうです


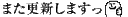
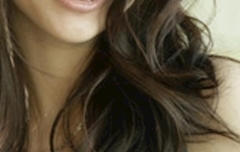
おやすみなさい